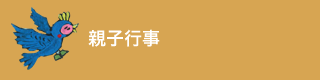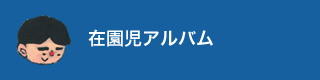水戸市笠原町の保育園・彩の国保育園。一時保育もお預けできます。
- トップ
- 保育雑感
保育雑感
No88.平成22年7月号 「小学校の授業参観」
卒園児を小学校へ送り出した後、子ども達が小学校でちゃんとやっているかどうかその様子を一度見て見たいと常々思っていましたが、やっとその夢が叶いました。緑岡小学校から、出身保育園・幼稚園の先生達に、授業参観のお誘いのお手紙が届きました。親になったような気持ちで、晃汰君、羽音ちゃん、楓ちゃんが待つ教室にソワソワしながら出掛けて行くと、はてなカードと筆記用具を入れた探検バックを肩からぶら下げて、大勢の生徒達に混じって真剣な顔で先生の話を聞いている3人の子ども達の姿が目に入ってきました。これから勉学に勤しみ沢山の知識を吸収し、色々な試練を乗り越えて行くべくスタート地点に元気に立っている子ども達に「がんばれ!」と心の中でエールを送りました。参観後、懇談会があり、感想や意見を交換しました。この集まりは「幼保連絡協議会」の第一回目で、相互に連絡を取り合い、教育効果を上げていこうというものだそうです。小学校からの要望として、基本的習慣(食べ方、椅子の座り方、トイレの使い方、廊下の歩き方など)の指導と、自分の名前の読み書き、時計を見て生活する習慣を身に付けてきて欲しいという話がありました。保育士と小学校教諭の連携が進むと、卒園児のその後の心配がいくらか少なくなるかもしれませんが、授業参観は続けて欲しいものです。
No87.平成22年6月号 「春の遠足」
遠足先に動物園を選んだのは初めての事でしたが、子ども達の反応は今までで一番良かったように思います。家族で行ったことがある子ども達も多いようですが、先生、友達と行くとまた違う楽しみ、喜びを感じるようです。帰宅後、いっぱい遠足の話を聞かせてくれたという保護者の方からのご報告や遠足後描いた絵からも、子ども達の心に印象深く残ったことがうかがえました。平常保育では見られない子どもの一面や内面にも接することができましたし、集団行動の学習面でも大いに効果がありました。私達保育士も、童心に返って一緒に動物を見て回り、大人も子どもも楽しませてくれる動物園の良さを再発見した遠足でした。
No86.平成22年5月号 「じゃがいもの種植え」
活気ある新年度が始まって1ヶ月が経とうとしています。新入児、進級児も新しいクラスに徐々に慣れ、日々の生活を楽しんでいます。卒園児からの便りも多数届き、みんな元気に新たな小学校生活を満喫しているようで、ほっと胸を撫で下ろしているところです。
さて、先日、クラスごとにじゃがいもの種植えをしましたが、学年が違えば植え方も様々。一列に並んで、穴の空いている場所に種芋をそっと置いて土を被せるはずが、ぽーんと投げ入れる子、優しく優しく両手で置いてあげる子、土をはらはらと舞う雪のようにかけてあげる子、ここほれワンワンとばかりに全く違う場所を掘り出す子…。きっと子ども達のような個性的なじゃが芋ができあがることでしょう。最後には「大きくなぁれ、大きくなぁれ」とおまじないをかけました。毎日雨が降り続いていますが、少しずつ芽が成長しています。じゃが芋の成長と共に、「大きくなぁれ」と元気いっぱいの子ども達の成長を祈り、今年の種植えを終えました。
さて、先日、クラスごとにじゃがいもの種植えをしましたが、学年が違えば植え方も様々。一列に並んで、穴の空いている場所に種芋をそっと置いて土を被せるはずが、ぽーんと投げ入れる子、優しく優しく両手で置いてあげる子、土をはらはらと舞う雪のようにかけてあげる子、ここほれワンワンとばかりに全く違う場所を掘り出す子…。きっと子ども達のような個性的なじゃが芋ができあがることでしょう。最後には「大きくなぁれ、大きくなぁれ」とおまじないをかけました。毎日雨が降り続いていますが、少しずつ芽が成長しています。じゃが芋の成長と共に、「大きくなぁれ」と元気いっぱいの子ども達の成長を祈り、今年の種植えを終えました。
No85.平成22年4月号 「卒園式―受け継がれるもの―」
第14回卒園式が、24日に行われ、過去最多の14名が彩の国保育園を巣立っていきました。涙もろい方が多く、涙涙の卒園式でした。今年の卒園児の素晴らしいところは、女児も男児も小さい子の面倒をよく見ることでした。土曜日のヒヨコ組の給食時は、お手伝いの年長さんでいっぱいで、先生顔負けの保育士ぶりの子もいました。小さい者を思いやる心は、確実に年中さんに引き継がれようとしており、彩の国の伝統となることでしょう。14名の卒園生達、どうもありがとう。そして、自信を持って、小学校の門をくぐり、入学式に臨んでください。
No84.平成22年3月号 「子どもは風の子」
今年の冬は久しぶりに雪の多い冬が日本に戻ってきました。暖冬で雪や氷が子どもの冬遊びから姿を消してしまうのではと心配していましたが、今年は雪だるま、雪うさぎ、かまくら作りや雪合戦と、雪と戯れる子どもの姿を見ることができました。寒い冬は子どもの体力と気力を養ってくれます。「子どもは風の子」という言葉も死語になりつつありますが、北風の中で子ども達は寒さに負けずにいっぱい遊びました。そのせいか、風邪をひく子が少なかったようです。冬季オリンピック出場の選手達の厳しい練習は、冬の寒さによって鍛えられた強い意志に支えられているのかもしれませんね。
No83.平成22年2月号 「餅つき大会」
餅つきに用いる杵と臼は、近所の山上さんが、家ではもう使う事もないので自由に使って下さいと、毎年快く貸してくださる物です。重い杵の扱いも回を重ねるごとに上手になり、年長男子は、何と一人で杵を持ち上げてついていました。無添加、つきたてのお餅のおいしいことおいしいこと、「おかわり!」の元気な声が飛びかっていました。山上夫妻はご高齢ですが、ご主人は毎日散歩を欠かさず、奥様は出来合いのおかずを買ったことが無い手作りにこだわる健康的な生活を送っているからでしょうか、矍鑠としています。見習いたいものです。22年が、「ぺったん、ぺったん」と言う元気な掛け声と共に、スタートしました。今年も健康で楽しい保育園生活が営まれることを願います。
No82.平成22年1月号 「サンタクロースは誰?」
クリスマス会には、毎年先生がサンタに扮して皆にお菓子をプレゼントしますが、「○○先生だー!」とすぐにばれてしまうのが通例でした。しかし、今年は最後まで本当のサンタクロースだと信じ込ませることに成功しました。昨年「恵美子先生だ!」コールに懲りた恵美子先生一策を考じ、白いひげと黒ぶち眼鏡で登場。一瞬場が静まり返り、ヒヨコ組の子供達は目が点に。お菓子を渡そうとすると逃げ出す子も。しかし、担任している子供は流石に変だと感じたようで「恵美子先生いない。」とつぶやき、先生達も大笑いのクリスマス会でした。今年も残すところ後僅か、新型インフルエンザの嵐も去り、穏やかな新年を迎えることができそうです。来年初の行事は餅つき大会です。お楽しみに…
No81.平成21年12月号 「運動会」
大勢の保護者の皆様の御参加により、楽しく賑やかに運動会を行う事ができました。子ども達はお父さんお母さんに見守られる中,練習の成果を余すことなく発揮し、達成感と満足感を十分味わったことと思われます。また、新しい企画として、親子競技や親子昼食を取り入れてみましたが、子ども達は、運動会を更に楽しく感じられたのではないでしょうか。子ども達の毎日の練習と当日のパフォーマンスを見る中で毎年感じることですが、運動会は体と心を鍛えるすばらしい保育行事だと思います。予行練習の時、転んだ、できない、勝負に負けたと言って泣く子が続出。そんな子ども達にエールを送る為に、運動会当日、「勝負に負けても自分の気持ちに勝つ」という言葉を贈りました。特に就学を控えた年長児にとっては、努力と協力、そして勝ち負けの意味を知り克己心を培う最良の機会です。私達保育士にとっても、日々の保育を見直すよい機会でもあります。これを機会に、更に努力していきたいと思います
No80.平成21年11月号 「子ども達に贈る小さな音楽会」
今年の音楽会は、物語を歌と音楽で綴るという新しい企画でしたが、大変好評でした。歌、合奏、踊りどれも練習の成果を十分発揮できました。毎日の練習に根を上げることもなく、「上手になりたい」という一心で頑張る子供達を見ていると、成長のエネルギーが感じられました。幼児期の「伸びようとする力」は発芽した芽のようなもので、日ごとにぐんぐん伸びていきます。芽が土と太陽と水を必要とするように、成長する環境を子ども達に整えてあげることが私達の仕事ですが、子どもの伸びようとする力が持つ可能性は、私達が考える以上に大きいものです。子供達のパワーに負けないように私達保育士も切磋琢磨しなければならないと感じた音楽会でした。
No79.平成21年10月号 「老人福祉施設との交流」
9月21日の敬老の日にグループホーム「ハイブリッジ」の敬老会にパンダ組が参加しました。元気な歌声と子供達が焼いたクッキーにホームの方々はとても喜んで下さいました。先月も「ヘルサ」の夏祭りに招待されて、お年寄りとの交流を持ちました。施設を訪れていつも感じることは、そこで働くヘルパーさんが明るく生き生きしているということです。老人と子どもの交流ばかりでなく、ヘルパーと保育士の交流の機会としても考えていけば、さらに意味のある施設間交流になると思います。老人と子供が共存していく人間性豊かな社会の実現のために、ヘルパーと保育士が力を合わせる必要があるでしょう。これからもどんどん交流の機会をもちたいと思います。今年も音楽会には「ヘルサ」のお年寄りを招待しています。ヘルパーさん達に負けない笑顔で迎えたいものです。
No78.平成21年9月号 「新型インフルエンザ対策について」
茨城県で初めての新型インフルエンザの患者が発生して以来、県の保健課、及び市の子ども課の通達を基に、保育園としての対応を御父兄の皆様方にご協力をお願いして参りました。現在まで幸いにも罹患者の発生は無く、通常の保育を続けることができました。しかし、夏休みが明け、新学期が始まると同時に新型インフルエンザの本格的流行が懸念されておりますし、乳幼児の重症化の症例も報告されています。この様な状況の中では、新型インフルエンザの発生に備えて、保育園としても、その対応を考えざるを得ません。県からの通達を別紙で配布致しますので、内容をご理解いただき、今後の経過を見守ると同時に、各ご家庭におかれましても、うがい・手洗いの励行、人込みを避ける、体調管理等に今まで以上に気を配り、予防に努めて頂きたく存じます。万が一発生した場合には、関係各担当課と相談した上で、園としての対策を立てる予定です。子どもの安全を第一に考え、臨時休園措置も視野に入れておりますので、各ご家庭におかれましても、ご準備をお願い致します。十年に一度などといわれるパンデミックを無事に乗り越えたいものです。ご理解、ご協力をお願い致します。
No77.平成21年8月号 「じゃが芋掘り」
春に植えつけたじゃが芋を収穫しました。昨年秋に収穫したさつま芋にはつるがあり、お芋の埋まっている場所が分かり易かったのですが、じゃが芋のつるは枯れてしまうので、宝探しのような面白さがありました。大きいお芋、小さいお芋、ハートの形、ミッキーの形、掘り出す度に歓声を上げるのがパンダさん。土を触るのが苦手な子がいるバンビさんも土に触れる機会が増す毎に、収穫を楽しむことができるようになってきています。ヒヨコさんは、お芋そっちのけで、蜘蛛の子を散らすように思い思いのところに歩いて行ってしまったり、手に取ったお芋をポイと投げ捨ててしまったりとあどけない行動が微笑ましい畑の風景でした。みんなが掘ったじゃが芋は給食の食材に使われて、子供達のお腹に納まります。
No76.平成21年7月号 「偕楽園梅落とし見学」
水戸藩九代藩主斉昭が「民と偕に楽しむ」と言う願いを込めて作ったといわれるだけあって、「偕楽園」は日本三大公園の中でも、最も私達一般市民がその恩恵を被る事が出来る素晴らしい公園だと感じます。特に「梅」は日本文化を支えてきたもので、庶民の生活にも深い関わりがあります。「食」に関しては、日本人の健康を支えてきた健康食品No1と言えるでしょう。彩の国でも毎年「偕楽園」のお陰で、子供達は沢山のことを学ぶことができます。路線バスの利用で公衆道徳を、梅落とし見学で偕楽園の歴史散策を、梅干し作りで伝統食文化をetc…とにかく子供達はこの一連の活動で大いに「偕に楽しむ」ことができました。梅干しの梅酢も順調に上がってきて、皆に食べられる日を待っています。
No75.平成21年6月号 「春の遠足」
春の遠足で森林公園に行くのは2年ぶりですが、子供達には人気が高い場所だと再確認しました。何と言っても山の斜面に作られた長い滑り台と、本物そっくりの恐竜が子供達には魅力なのでしょう。バンビさんは3グループに分かれて、ロープにつかまりながらの移動で迷子になる子もなく、自分のリュックを最後まで背負って歩き通しました。恐竜を全部見て回ったのは、年少さん。長いしっぽに跨り、みんなで写真も撮りました。年長、年中は担任の先生が、筋肉痛になる程滑り台で遊んできました。自然の中でいっぱい遊んで、美味しいお弁当をみんなで食べて、楽しい楽しい一日を過ごした子供達は、次の日それぞれの思いを画用紙の上に表現しました。
大人が考える以上に、遠足というのは子ども達にとってワクワクする行事なのでしょう。私達も遠い記憶をたどると、遠足の記憶は鮮明に残っていますものね。
大人が考える以上に、遠足というのは子ども達にとってワクワクする行事なのでしょう。私達も遠い記憶をたどると、遠足の記憶は鮮明に残っていますものね。
No74.平成21年5月号 「縦割り保育」
4月当初園内に響き渡っていた新入園児の鳴き声も納まり、新年度の活動が徐々に軌道に乗ってきました。新しい担任、新しいメンバーで各クラスとも活気に溢れている毎日です。クラス編成は、開園当初から「縦割り保育」と呼ばれる異年齢児集団のクラス形態ををとっていますが、異年齢間の関わりならではの保育効果が、年々顕著になって来ています。小さい子を慈しみ可愛がる気持ちを育み、大きい子を慕い憧れる気持ちを培うことは、人間社会の秩序を保ち健全な人間関係を造っていく上でとても大切なことです。「慈愛」や「礼節」などの古い言葉の中に、人間形成上大事なものが沢山有る様に感じます。赤ちゃんのお世話をする年長さんの姿や、喜んでいる赤ちゃんの笑顔に明るい未来が見えると言ったら大袈裟でしょうか。今年度も縦割りの良い所を充分に生かして日々の保育に努めていきたいと思います。
No73.平成21年4月号 「卒園登山」
毎年卒園児は、筑波山登頂を果たして卒園を迎えるのが恒例になっています。今年で5年目ですが、誰もが初めての経験なので、それほど高くない山とは言え、急登や岩場も多い為、果たして上まで登れるのかと不安を抱きながらの出発となります。ところが、今まで登頂を果たさなかった子が一人もいないと言う事は、運動能力も体力も6歳児は登山可能なレベルに達していると言えるでしょう。今年は、なんと60分という最短時間を記録しました。親子で登頂を果たし、気分も晴れやかにロープウェイで下山しながら、「子供がこんなに喜ぶなら、また山に登ってみたい。次回はもっと高い山にしよう。」という気持ちになるようです。が、残念ながら実行した報告は一つも届いてきません…冬の家族スキーに出かける方は多いようですが、夏の家族登山は余り人気がないのでしょうか。スキーもそうですが、気持ちがひとつになれる山登りは家族レジャーに最適だと思います。小学校6年生で富士登頂を目指して、家族登山を始めてみては如何でしょうか。因みに、つくばTX開通で登山客が急増し、今までになく頂上は人でごった返していました。
No72.平成21年3月号 「節分」
2月は3日の節分、14日のバレンタインと寒い時期楽しい行事が2つあります。食品業界の宣伝に乗せられて、恵方巻とチョコをみなさんも買ったことでしょう。子供達に人気が高いのは節分ですが、今年も園庭に「鬼は外、福は内」の元気な声が響き渡りました。食べる豆の数の話で盛り上がりました。自分の歳より1つ多い数だけ食べることを話して、4歳のK君の例をあげて、「4+1は?」と出題するとさすが年長さんは正確。しかし、保育士さん達は自分の食べる豆の数が計算できませんでした。「園長先生は何歳?」という問いに本当の歳を言ったら、「エ~~~~~~!!」とどよめきが起こりました。ショックを隠して「○7個も食べられるんだよ、いいでしょう。」と自慢してあげました。今月はひな祭りとホワイトデー。家族揃って季節の行事を楽しむことが少なくなってきている今日、ご家庭でも子供達と共に、季節に彩りを添える日本古来の行事を大切にしながら新しいイベントも大いに楽しんでみてはいかがでしょうか。
No71.平成21年2月号 「餅つき大会」
杵と臼を使って餅つきをする光景は、最近めったに目にすることができなくなっていますが、子ども達にとっては、とても興味津々な行事です。「ぺったんぺったん」と言う掛け声やそのリズム、杵を持ち上げて振り下ろす仕草、何よりもおいしいおいしいお餅が食べられること、バンビ、パンダ組はもとより、見学していたヒヨコ組のチビちゃん達も手ばたきしたり、身を乗り出したりととても楽しんでいました。何度も経験している年長さんの中には重い杵をひとりで持ち上げ上手に付く子もいました。毎年杵と臼を貸して下さる近所の老御夫妻は、昔近所の子を集めて餅つきをしていたそうです。地域の中で子どもを育てる社会の再生を目指す動きも少しずつ広がっています。日本古来の行事を大切にすることが、地域の繋がりや世代の交流を深めることに繋がるかもしれませんね。
No70.平成21年1月号 「今年を締めくくるクリスマス会」
今年のクリスマス会は、全園児が一同に会して、各クラスごとの発表を見て楽しみました。ヒヨコ組は帽子と手に星の鈴をつけて、バンビ組は女の子がトナカイ、男の子がサンタの帽子をつけて踊りました。パンダ組は合奏と劇を披露してくれましたが、各クラスとも今までの保育や行事の積み重ねによる成長が感じられる発表でした。最後にサンタさんが登場すると、子供達の目は一斉に輝き、クリスマス会はクライマックスに…
このクリスマス会で一年を締めくくりますが、今年を振り返ってみますと、世界が大きく変わろうとしていることが、生活の中で私達も日々実感した一年でした。特に食の安全の問題は、子ども達の健康ひいては命に関る由々しき出来事で、自分で自分を守るしかないと言う危機感さえ感じさせられます。保育園でも、食材の吟味や野菜作りで食の安全の手がかりを探りました。来年は明るいニュースが増えることを願って止みません。
このクリスマス会で一年を締めくくりますが、今年を振り返ってみますと、世界が大きく変わろうとしていることが、生活の中で私達も日々実感した一年でした。特に食の安全の問題は、子ども達の健康ひいては命に関る由々しき出来事で、自分で自分を守るしかないと言う危機感さえ感じさせられます。保育園でも、食材の吟味や野菜作りで食の安全の手がかりを探りました。来年は明るいニュースが増えることを願って止みません。
No69.平成20年12月号 「運動会」
お天気に恵まれて暖かい日差しの中、大勢の保護者の方々に声援をうけながら、子供達は思う存分運動会を楽しみました。皆様から沢山の感想を頂きましたが、お家では見られない、集団のなかでの我が子の姿を見て、「びっくりした」とか、「感動した」と言う声が多く聞かれました。競技ルールや団体行動が子供達の社会性や集団性を育み、ひいては社会規範を遵守し、善悪の判断ができる人間に育てるのに、運動会の果たす役割は大きいと感じます。勿論、厳しい練習や個性を無視した集団行動を押し付ける方法ではなく、幼児の本姓に合う又は一人一人にあう方法を試行錯誤しながら、子供達が進んで、そして楽しく活動できるかが、保育士の腕の見せ所です。今年は、物語を取り入れた競技で子供達の意欲を引き出しました。ヒヨコ組のアンパンマンのお話、バンビ組のせりふの入った劇風のポニョダンス、お花と蜂達のコラボダンスどれも物語の中でなりきって演じていました。衣装を持ち帰りましたので、お家でパパ、ママが参加して物語の続きを作ってください。T君は、さっそくパパに蜂ダンスを教えて、親子蜂になりきり、裸で踊ったそうです。(風呂上りなので)写真があるので見たい方は申し出てください。パパ蜂は写っていませんのでご安心下さい・・・
222件中 181-200件目