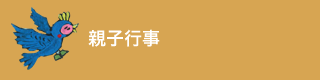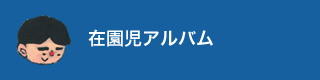水戸市笠原町の保育園・彩の国保育園。一時保育もお預けできます。
- トップ
- 保育雑感
保育雑感
No128.平成25年11月号 「卒園児の活躍を目にして…」
笠原小学校の2年生が、校外学習で彩の国保育園を訪れました。17名の小学生がやって来ると、園庭で遊んでいた子ども達は、予期せぬお客様に大喜び。小学生たちの周りは、あっという間に、黒山の人だかりに。卒園児のSちゃんとR君の姿を見つけると、またまた、大騒ぎ。園庭で、朝の全体集会が始まると、やっと興奮も収まり、一緒に体操をやりました。
その後、2グループに分かれてヒヨコ組とバンビ組のお手伝いをしてもらいましたが、卒園児2人は、小さい子のお世話はお手の物。他の子が、小さい子ども達とどうやって関わっていいのか戸惑っている中、Sちゃんは、泣いている赤ちゃんを抱っこしてあやし、R君は、進んで2歳児さんに話しかけて、お世話していました。彩の国保育園の縦割保育で培われた力を小学校の授業の中で発揮している姿を目の当たりにして、誇らしい気持ちになりました。
現在、子ども達は、毎日運動会の練習をしていますが、競技を通して、大きい子は小さい子のお世話をしています。一つの行事を取っても、保育園の毎日の生活や活動の中で、育まれるものが、血となり肉となり、成長の過程で試されながら、長い時間をかけて磨かれて行って欲しいと、この日思いました。
小学生が帰った後、K君が「明日も来てくれるかなあ?」と聞いてきました。本当に時々来てもらって、一緒に遊びたいものです。
その後、2グループに分かれてヒヨコ組とバンビ組のお手伝いをしてもらいましたが、卒園児2人は、小さい子のお世話はお手の物。他の子が、小さい子ども達とどうやって関わっていいのか戸惑っている中、Sちゃんは、泣いている赤ちゃんを抱っこしてあやし、R君は、進んで2歳児さんに話しかけて、お世話していました。彩の国保育園の縦割保育で培われた力を小学校の授業の中で発揮している姿を目の当たりにして、誇らしい気持ちになりました。
現在、子ども達は、毎日運動会の練習をしていますが、競技を通して、大きい子は小さい子のお世話をしています。一つの行事を取っても、保育園の毎日の生活や活動の中で、育まれるものが、血となり肉となり、成長の過程で試されながら、長い時間をかけて磨かれて行って欲しいと、この日思いました。
小学生が帰った後、K君が「明日も来てくれるかなあ?」と聞いてきました。本当に時々来てもらって、一緒に遊びたいものです。
No127.平成25年10月号 「秋の空」
台風18号の大風が吹いた9月16日の夕方、台風一過の空は、夕焼けと月がきれいな秋の訪れを感じさせる爽やかな夕暮れでした。ヒヨコ組のテラスで、子ども達と移りゆく空の色や、雲に見え隠れする月を、30分以上も眺めていました。「オレンジ、青、水色、紫、緑色もあるよ!全部で5つもあるよ!」「月には、うさぎとくまとかにがいるんだよ。」「パンダもいるんだよ。」「♪夕焼け小焼けでまたあした…♪」
T君が、夕焼けの空に触発されて、先日の音楽会で歌った歌を口ずさみ始めたのを見て、以前読んだ本のタイトルを思い出しました。「子どものセンスは夕焼けがつくる」という本でしたが、作者に共感を覚えた出来事でした。
この3日後の十五夜もすばらしい秋空でした。今年の十五夜(旧暦8月15日)は、8年後にしか見られない満月ということで、オリンピックよりもっと先のことかと、しみじみと月を眺めました。正式に月見団子と里芋(収穫に感謝する)とすすき(魔除け)も飾りました。
保育園のおやつにも団子を作りましたが、団子を一度も口にしたことがないH君が、家に帰り「もっと食べたい!」とママにねだったそうです。その夜、中秋の名月に照らされながら、パパと2人でセブンイレブンに団子を買いに行ったそうです。
ちなみに、先生達の子どもの頃は、お月見をしたか聞いてみたところ、「やった」が7人、「やらない」が4人でした。皆様のご家庭ではやりましたか?もしやらなかった人も、十三夜が10月17日、十日夜が11月12日にあるので、ぜひ、お月見を楽しんでください。
T君が、夕焼けの空に触発されて、先日の音楽会で歌った歌を口ずさみ始めたのを見て、以前読んだ本のタイトルを思い出しました。「子どものセンスは夕焼けがつくる」という本でしたが、作者に共感を覚えた出来事でした。
この3日後の十五夜もすばらしい秋空でした。今年の十五夜(旧暦8月15日)は、8年後にしか見られない満月ということで、オリンピックよりもっと先のことかと、しみじみと月を眺めました。正式に月見団子と里芋(収穫に感謝する)とすすき(魔除け)も飾りました。
保育園のおやつにも団子を作りましたが、団子を一度も口にしたことがないH君が、家に帰り「もっと食べたい!」とママにねだったそうです。その夜、中秋の名月に照らされながら、パパと2人でセブンイレブンに団子を買いに行ったそうです。
ちなみに、先生達の子どもの頃は、お月見をしたか聞いてみたところ、「やった」が7人、「やらない」が4人でした。皆様のご家庭ではやりましたか?もしやらなかった人も、十三夜が10月17日、十日夜が11月12日にあるので、ぜひ、お月見を楽しんでください。
No126.平成25年9月号 「音楽会~新たな試みへ~」
音楽会を一週間後に控え、今、保育園ではヒヨコ組からパンダ組まで、一同に会して練習する、賑やかな光景が毎日のように見られます。
今年で13回目となる彩の国保育園の音楽会は、当初、「音楽家の演奏を生で聴く」音楽会としてスタートしましたが、音楽家とのコラボレーションによるパンダ組の子ども達の発表を加えて、徐々に内容を発展させてきました。
今年は、また、新たな試みとして、全園児が舞台に立ち、発表を行います。
彩の国保育園の大きな特徴の一つが、0歳児から6歳児までの異年齢の関わりを大切にする縦割り保育の実践ですが、それにより子ども同士は、日々、親近感や信頼感に支えられて互いに切磋琢磨し合い、成長を遂げています。そんな日々の縦割り保育の良さを、保護者の方々に、全園児での楽しい劇遊びで観ていただきたいという思いがありました。
しかし、不安材料も多く、なかなか実行できないでおりましたが、ヒヨコ組やバンビ組の子ども達にもスポットを当てた音楽会を望む保護者の方々の要望も年々多くなってきたことが後押しとなり、本年度は、全園児による音楽会を開催すべく準備してきました。
ステージの上で、多くの観客を前に、小さな子ども達は、どんな反応を示すのか、未知のものがあります。新しい試みの音楽会ですが、どうか、子ども達の挑戦に客席から温かいエールをお願い致します。
今年で13回目となる彩の国保育園の音楽会は、当初、「音楽家の演奏を生で聴く」音楽会としてスタートしましたが、音楽家とのコラボレーションによるパンダ組の子ども達の発表を加えて、徐々に内容を発展させてきました。
今年は、また、新たな試みとして、全園児が舞台に立ち、発表を行います。
彩の国保育園の大きな特徴の一つが、0歳児から6歳児までの異年齢の関わりを大切にする縦割り保育の実践ですが、それにより子ども同士は、日々、親近感や信頼感に支えられて互いに切磋琢磨し合い、成長を遂げています。そんな日々の縦割り保育の良さを、保護者の方々に、全園児での楽しい劇遊びで観ていただきたいという思いがありました。
しかし、不安材料も多く、なかなか実行できないでおりましたが、ヒヨコ組やバンビ組の子ども達にもスポットを当てた音楽会を望む保護者の方々の要望も年々多くなってきたことが後押しとなり、本年度は、全園児による音楽会を開催すべく準備してきました。
ステージの上で、多くの観客を前に、小さな子ども達は、どんな反応を示すのか、未知のものがあります。新しい試みの音楽会ですが、どうか、子ども達の挑戦に客席から温かいエールをお願い致します。
No125.平成25年8月号 「お泊り保育 ~卒園児と一緒に夏祭り~」
7月恒例のお泊り保育が、28日に行われます。今年は、卒園生が大勢参加を希望してきました。1~3年生までの16名が保育園に集合します。彩の国保育園での体験を楽しい思い出として記憶に留め、保育園を忘れずにこうして集ってくれることは、私達にとって、保育士冥利に尽きる喜びです。元気に大きく成長した姿を見るにつけ、保育士という仕事に誇りとやりがいを感じずにはおられません。
在園児もまた、小学生のお兄さんお姉さん達と一緒にお泊り保育ができることをとても楽しみにしています。そこで今年は、出店の店員を、卒園生にやってもらい、夏祭りを園庭で行うことになりました。子ども達はお祭りが大好きです。特に、立ち並ぶ出店の中を両親に連れられて、お目当ての出店でお目当ての物を買ってもらう喜びは、一生忘れられない記憶として子どもの心に刻まれます。皆様の家庭でも、様々な楽しいお祭り体験があることと思います。
余談ですが、先生達に、子どもの頃の忘れられないお祭りの楽しかった思い出は何か聞いてみました。射的が得意だった父親に欲しい的を撃ち落としてもらったこと、両親と一緒に踊った盆踊り、子供会で引いた山車の後にもらったアイスの味、出店の金魚すくい、ヨーヨー、綿あめ、リンゴ飴、お好み焼きなどなど、昔から変わらぬ定番メニューが続々と出てきました。さて、今回の夏祭りではどんな出店が並ぶのでしょうか。子ども達が大人になっても忘れない夏祭りになることを願っています。
在園児もまた、小学生のお兄さんお姉さん達と一緒にお泊り保育ができることをとても楽しみにしています。そこで今年は、出店の店員を、卒園生にやってもらい、夏祭りを園庭で行うことになりました。子ども達はお祭りが大好きです。特に、立ち並ぶ出店の中を両親に連れられて、お目当ての出店でお目当ての物を買ってもらう喜びは、一生忘れられない記憶として子どもの心に刻まれます。皆様の家庭でも、様々な楽しいお祭り体験があることと思います。
余談ですが、先生達に、子どもの頃の忘れられないお祭りの楽しかった思い出は何か聞いてみました。射的が得意だった父親に欲しい的を撃ち落としてもらったこと、両親と一緒に踊った盆踊り、子供会で引いた山車の後にもらったアイスの味、出店の金魚すくい、ヨーヨー、綿あめ、リンゴ飴、お好み焼きなどなど、昔から変わらぬ定番メニューが続々と出てきました。さて、今回の夏祭りではどんな出店が並ぶのでしょうか。子ども達が大人になっても忘れない夏祭りになることを願っています。
No124.平成25年7月号 「尾山先生の虫歯予防アドバイス」
先日、歯科検診がありましたが、園医の尾山先生に今年の傾向と子どもの歯を虫歯から守る為のアドバイスを伺いました。今年は、昨年までと比べると、虫歯が増加しているそうです。特に、上下とも前歯の正中の歯の虫歯が目立ちます。歯垢、歯石については、幼児は唾液が多いのでほとんど目立たないのですが、下の前歯に歯垢がついている子も見られたということです。虫歯は、口の中のpHが酸性に傾くと発生してくるので、甘いものが長時間口の中にあると酸性状態が持続するので虫歯になりやすいそうです。だから、アメを長い時間なめたり、お菓子のダラダラ食べは禁物です。時間を決めて短い時間に済ませることが大切です。
予防の基本は、歯ブラシによる歯磨きですが、(電動歯ブラシはよくないそうです!)食べた直後は歯の表面が柔らかく、歯ブラシで傷つきやすいので、食後20~30分が良いそうです。食事直後には、水でうがいをするとよいということです。
また、定期検診は6ケ月ごとに受け、フッ素塗布することで、発生率は低くなります。歯磨き、うがい、定期検診の習慣を身に着けさせ、子どもの一生の健康を左右する歯を、虫歯から守ってあげましょう。
ちなみに、先生たちの虫歯(治療歯も含む)の平均本数は、5.7本でした。私達大人も、80歳自歯20本を目指して予防に心掛けましょう。
No123.平成25年6月号 「子どもの頃の遊び」
春の遠足のH君の「べーごま」発言に触発されて、子どもの頃の遊びに思いを馳せてみました。子どもの頃の楽しかった思い出は、ほとんどが遊んだ記憶と言っても過言ではないと思いますが、数ある遊びの中で自分が一番楽しかった思い出の遊びは、と聞かれたら、何と答えますか?
先生達に聞いてみたところ、おままごと、竹馬、一輪車、ドレスを着てお姫様ごっこ、衣装を着てごっこ遊び、落とし穴作り、お砂遊び、サイクリング、ドッジボール、木登り、川遊び…世代や環境によって遊びも様々でしょうが、子どもの頃の遊びが人間形成に欠かせないとするなら、自分の遊び史を振り返って、大切だと思う遊びを自分の子どもに教え伝えるのも親の役目かもしれませんね。
先生達に聞いてみたところ、おままごと、竹馬、一輪車、ドレスを着てお姫様ごっこ、衣装を着てごっこ遊び、落とし穴作り、お砂遊び、サイクリング、ドッジボール、木登り、川遊び…世代や環境によって遊びも様々でしょうが、子どもの頃の遊びが人間形成に欠かせないとするなら、自分の遊び史を振り返って、大切だと思う遊びを自分の子どもに教え伝えるのも親の役目かもしれませんね。
No122.平成25年5月号 「柏餅、小豆餡と味噌餡どっちが好き?」
端午の節句(子どもの日)と言えば、鯉のぼりに菖蒲、粽(ちまき)に柏餅ですが、もともと邪気を払う節句だったものが、江戸時代後半から男の子の節句として定着し、今に至っているそうです。菖蒲や粽を巻く茅(ちがや)の葉は、邪気を払い難を避けるものとして、鯉や柏は男児繁栄の縁起物として用いられたという由来があります。
ところで、柏餅には小豆餡と味噌餡の二種類がありますが、みなさんはどちらが好きですか?ちなみに、先生達は、9対3で小豆派が味噌派の3倍でした。中身を区別する為に、小豆は柏の葉の裏側を表に、味噌は葉の表側を表にして包まれています。たかが柏餅一つですが、親から子へ、子から孫へという伝統行事を次の世代につないでいく上で、行事にまつわる食文化は、大事な役割を担っています。親の情愛を、食べ物を通して子に伝える良い機会でもあります。どうぞ、ご家族で楽しい子どもの日をお過ごしください。子ども達は、どっちが好きかな?粽も食べてね。菖蒲湯も!
ところで、柏餅には小豆餡と味噌餡の二種類がありますが、みなさんはどちらが好きですか?ちなみに、先生達は、9対3で小豆派が味噌派の3倍でした。中身を区別する為に、小豆は柏の葉の裏側を表に、味噌は葉の表側を表にして包まれています。たかが柏餅一つですが、親から子へ、子から孫へという伝統行事を次の世代につないでいく上で、行事にまつわる食文化は、大事な役割を担っています。親の情愛を、食べ物を通して子に伝える良い機会でもあります。どうぞ、ご家族で楽しい子どもの日をお過ごしください。子ども達は、どっちが好きかな?粽も食べてね。菖蒲湯も!
№121,平成25年4月 「卒園式」
3月15日、梅の花が満開に咲き誇る春の日に、卒園生14名が目出度く彩の国保育園を巣立っていきました。歌、ピアニカ演奏、卒園の言葉など堂々と見事にやり遂げました。4月には小学校に入学する訳ですが、時代が変われば、地域や国が変われば「就学」できない子供達が大勢いることに思いをはせ、就学させることができる喜びを噛みしめました。みんなしっかり勉強して、立派な大人になってください。
No120.平成25年3月号 「うれしいひなまつり」
子どもの歌は、明るい長調の曲が圧倒的に多く、悲しい短調の曲はあまりありませんが、この時期よく歌われる「たのしいひなまつり」は短調の曲です。哀調を帯びた悲しい曲想にしたことで日本情緒がよく表現されています。また、この曲に限らず童謡には、「四七抜き音階」(ドレミの音階からファとシを除いたもの)が多く、日本古来の「五音音階」が故に私たち日本人の心情に訴えかけてくるのでしょう。民謡や演歌もこの音階が使われているものがいっぱいあります。
ちなみにこの曲の作詞はサトウハチローですが「出来る事ならこの曲を捨ててしまいたい。」というほ
ど嫌っていたとか。その訳は、歌詞中2ケ所誤りがあるからだそうです。どこだかわかりますか?
ちなみにこの曲の作詞はサトウハチローですが「出来る事ならこの曲を捨ててしまいたい。」というほ
ど嫌っていたとか。その訳は、歌詞中2ケ所誤りがあるからだそうです。どこだかわかりますか?
No119.平成25年2月 「常(とこ)若(わか)」
年が明けて最初の行事である「餅つき大会」が、風もなく暖かいお天気に恵まれたなか、園庭で賑やかに行われました。見学にいらっしゃった保護者の方々にも、臼と杵で餅つきを体験して頂きました。餅つき経験のあるお父さんが餅をつくと、杵使いの技の上手さとその迫力に、子供達と保育士達は圧倒され、大興奮でした。今年用いた杵は、昨年までの大きく重い杵ではなく、パンダ組のh君のおじいちゃんが、子供用に改造してくれた杵です。杵を作ってくれたおじいちゃんと、杵で餅をついてくれたお父さんの「昔取った杵柄」の知恵と経験のお蔭で、例年以上に楽しい「餅つき大会」となりました。
「ぺったん、ぺったん」という元気な掛け声と共に、彩の国保育園の2013年は目出度くスタートを切りました。
2013年=平成25年は日本にとって奇跡の年と言われています。というのは、日本の神々が宿る伊勢神宮と出雲大社の御遷宮が重なる一生に一度あるかないかの特別な年だからです。(伊勢神宮は20年に一度、出雲大社は60年ぶり)遷宮とは、神社などで一定の年数を定めて社殿を修理、造営し、新しい社殿に御神体を遷すことです。遷宮の由来は、日本特有の「常(とこ)若(わか)」という思想から生まれたと言われています。常に若々しく、瑞々しくある状態を「常若」と言いますが、「原点回帰」とか「古くて新しい」という言葉に置き換えて解釈することもできると思います。危機感や閉塞感のある大変な時代であっても、私達日本人の血の中に受け継がれている、遠い昔の先人達の叡智を思い起こし、忘れないように努め、今年もまた一年、子供達と共に歩み進みましょう。
「ぺったん、ぺったん」という元気な掛け声と共に、彩の国保育園の2013年は目出度くスタートを切りました。
2013年=平成25年は日本にとって奇跡の年と言われています。というのは、日本の神々が宿る伊勢神宮と出雲大社の御遷宮が重なる一生に一度あるかないかの特別な年だからです。(伊勢神宮は20年に一度、出雲大社は60年ぶり)遷宮とは、神社などで一定の年数を定めて社殿を修理、造営し、新しい社殿に御神体を遷すことです。遷宮の由来は、日本特有の「常(とこ)若(わか)」という思想から生まれたと言われています。常に若々しく、瑞々しくある状態を「常若」と言いますが、「原点回帰」とか「古くて新しい」という言葉に置き換えて解釈することもできると思います。危機感や閉塞感のある大変な時代であっても、私達日本人の血の中に受け継がれている、遠い昔の先人達の叡智を思い起こし、忘れないように努め、今年もまた一年、子供達と共に歩み進みましょう。
No118.平成25年1月号 「クリスマスとお正月どっちが楽しい?」
昨日、クリスマス会を行いました。ヒヨコは、赤いマントを着けサンタになって、「赤鼻のトナカイ」の曲に合わせて、ダンスを披露。バンビは「山の音楽家」の曲を用いた劇と、手遊びを発表。パンダは、音楽会で歌った「静かなクリスマス」と「ハッピーチルドレン」の2曲を大合唱。どのクラスも日頃の保育の中で楽しんで活動している様子がうかがわれる発表でした。大塩先生手作りのブラブラサンタペープサートが大受け。また、どこから来たのか黒縁メガネのサンタクロースのユーモラスなジェスチャーにも大喜び。みんなでいっぱい笑ったクリスマス会でした。ご家庭でもケーキやプレゼントを用意して、楽しいパーティーを企画していることでしょうが、クリスマスが終わったら、日本古来のお正月が控えています。伝統や風習を子供達に伝え日本文化のすばらしさをたやさないようにしたいものです。おせち料理は、クリスマス料理にはみられない、食の知恵がこめられています。羽根つき、独楽、凧揚げ、福笑い等等の正月遊びは百年昔、千年昔から続いています。おせちを食べて、お年玉をもらって、家族でかるたを楽しんだ子どもの頃の記憶は、いくつになっても忘れません。クリスマスもお正月もどちらも優劣つけがたい。子供心に戻って、お子様と楽しい年末年始をお過ごし下さい。
No117.平成24年12月号 「速し、楽し、忙し師走」
暑く長かった夏の印象を引きずりながら、秋を満喫しないうちに、いつの間にか、気が付くと路上のかえでの葉っぱが木枯らしに舞い踊る季節になっていました。12月が近づくと時の流れの速さに驚き、ふと、立ち止ってしまいます。
保育室からは「♪百の物語が百年繰り返す~千の物語が千年繰り返す~遠い窓に灯りがともる♪~」と永遠の時を刻み続けてきた人間の営みを慈しむような歌詞に載せて、子供達の可愛い歌声が聞こえてきて、また、ふと足を止めます。感傷に浸って一年を振り返りかけたら、「♪ハッピー、ハッピー、ハッピーチルドレン♪~」と、窓ガラスが割れんばかりの元気な歌声に背中を押されて、まだまだ一年は終わってないんだ忙し忙しと、今度は師走走りになってしまいました。音楽会に向けた子供達の猛練習はこれからが大詰めです。保護者の皆様もお忙しいこととは思いますが、音楽会を楽しみにお待ち頂き、笑顔で師走をお迎え下さい。
保育室からは「♪百の物語が百年繰り返す~千の物語が千年繰り返す~遠い窓に灯りがともる♪~」と永遠の時を刻み続けてきた人間の営みを慈しむような歌詞に載せて、子供達の可愛い歌声が聞こえてきて、また、ふと足を止めます。感傷に浸って一年を振り返りかけたら、「♪ハッピー、ハッピー、ハッピーチルドレン♪~」と、窓ガラスが割れんばかりの元気な歌声に背中を押されて、まだまだ一年は終わってないんだ忙し忙しと、今度は師走走りになってしまいました。音楽会に向けた子供達の猛練習はこれからが大詰めです。保護者の皆様もお忙しいこととは思いますが、音楽会を楽しみにお待ち頂き、笑顔で師走をお迎え下さい。
No116.平成24年11月号 「運動会と音楽会」
秋から冬にかけて、運動会と音楽会の二大イベントが続く中で、子供達、特にパンダ組さんは、練習、練習の毎日です。この二つの行事の成果は、まさに秋の実りさながらです。運動会では、練習を重ねることでひとりひとりの発育、発達が促され、昨日できなかったことが今日できるという目覚ましい成長が見られました。また、集団の一員としての態度や行動を学び、集団の規律や力を合わせる大切さの理解も深まったことでしょう。運動会の競技の中で、最も感動を呼ぶのが集団演技ですが、規律正しく、皆と力をあわせる子供達の姿に、涙したご父兄も多かったことでしょう。社会の中で生きていく人間として、真摯でひたむきな和を重んじる精神が集団演技には宿っているからなのでしょうか?ご自分の子供が出ていないのに、涙が出てしまったという方が何人もいらっしゃいました。
さて、音楽会でも子供達は、成長の階段を一歩一歩登ります。今年は、「くるみ割り人形」ですが、クリスマスの夜に繰り広げられる不思議な物語を、歌と踊りで表現します。例年のごとく、プロの音楽家の方々に加え、今年はバレリーナーも参加して頂き、クラシックバレーの舞台の雰囲気を取り入れてみました。クラシックバレーの素晴らしさは、集団の規律ある仕組みと明確な配役分担、ソリストとコール・ド・バレエの対比の面白さ、そして全員にスポットがあたり拍手を受けられる舞台進行の仕方にあると思いますが、それにあやかって、子供達もみんなで力を合わせて練習に励み、ひとつの舞台を作る中で、自分の役割を掴み、成長の糧を得て欲しいと思います。ちなみに、「くるみ割り人形」は色々なバレー団で公演が予定されていますが、この度、世界文化賞を受賞した森下洋子(還暦を過ぎてもプリマとして活躍している世界的プリマバレリーナー)の舞台がお勧めです。
さて、音楽会でも子供達は、成長の階段を一歩一歩登ります。今年は、「くるみ割り人形」ですが、クリスマスの夜に繰り広げられる不思議な物語を、歌と踊りで表現します。例年のごとく、プロの音楽家の方々に加え、今年はバレリーナーも参加して頂き、クラシックバレーの舞台の雰囲気を取り入れてみました。クラシックバレーの素晴らしさは、集団の規律ある仕組みと明確な配役分担、ソリストとコール・ド・バレエの対比の面白さ、そして全員にスポットがあたり拍手を受けられる舞台進行の仕方にあると思いますが、それにあやかって、子供達もみんなで力を合わせて練習に励み、ひとつの舞台を作る中で、自分の役割を掴み、成長の糧を得て欲しいと思います。ちなみに、「くるみ割り人形」は色々なバレー団で公演が予定されていますが、この度、世界文化賞を受賞した森下洋子(還暦を過ぎてもプリマとして活躍している世界的プリマバレリーナー)の舞台がお勧めです。
No115.平成24年10月号 「秋の登山の勧め」
昨日、卒園児である3年生のK君が、久しぶりに保育園を訪ねて来てくれました。K君のご両親は共に体育大卒業で、大のスポーツ愛好家。子どもの習い事は、空手にスイミングに体操に野球。そして、卒園遠足での筑波山登山以来、富士登山に憧れ、家族全員(男4女1のファブリーズファミリー)で富士の山頂に立つのが夢!まずは父親と長男のK君が登頂に成功し、来年は年長になる次男も山頂を目指すとか。登山の話で盛り上がり、私が先日、日本で2番目に高い山に登ってきた話をすると、K君の目がキラリ。そういえば、富士登山に成功した小学3年生の男の子に山で出会いましたが、その父親曰く、「今度は2番目の山に登りたい!」と言うので連れてきたと言っていました。北岳3193mの山頂で、「次は3番目の山に登りたい!」と、きっとその子は思ったことでしょう。
ちなみに、日本の高い山ベスト5は、1、富士山(3,776m)2、北岳(3,193m)3、奥穂高岳(3,190m)4、間の岳(3,189m)5、槍ヶ岳(3,180m)です。
未来のアルピニストの為に、世界の高い山ベスト5もあげておきましょう。1、エベレスト(8,848m)2、K2(8,611m)3、カチェンジェンガ(8,586m)4、ローツェ(8,516m)5、マカルー(8,463m)。
スポーツの秋、運動会も近づき、園児達は毎日練習に励んでいます。ご家庭でも、家族でスポーツをお楽しみください。山登り、お勧めですよ…!
ちなみに、日本の高い山ベスト5は、1、富士山(3,776m)2、北岳(3,193m)3、奥穂高岳(3,190m)4、間の岳(3,189m)5、槍ヶ岳(3,180m)です。
未来のアルピニストの為に、世界の高い山ベスト5もあげておきましょう。1、エベレスト(8,848m)2、K2(8,611m)3、カチェンジェンガ(8,586m)4、ローツェ(8,516m)5、マカルー(8,463m)。
スポーツの秋、運動会も近づき、園児達は毎日練習に励んでいます。ご家庭でも、家族でスポーツをお楽しみください。山登り、お勧めですよ…!
No114.平成24年9月号 「岡島先生を悼む」
調理師として、長年に渡り子ども達に美味しい給食を作ってくれていた岡島節子先生が、8月17日にお亡くなりになりました。昨年7月から闘病生活に入りましたが、辛いはずの抗がん剤治療も笑顔で乗り切り、治ったらまた子ども達に給食を作ると約束していました。温かいものは温かいうちに、一味工夫して子どもの口に合うものを、と20年間のレストラン経営の料理人のプライドと子どもを想う慈愛に満ち溢れた人間性で、彩の国保育園を台所から支えてくれていました。私達にとって、かけがえのない先生でした。
コーヒーが好きでした。その人生は、コーヒーのように薫り高く、周囲の人を癒してくれました。
フェルメールが好きでした。その人生は、強い意志を優しい光で包んだフェルメールの絵のように魅力的でした。
命あるものいずれは死と向かい合わなければなりませんが、最期まで人を気遣いながら旅立たれた岡島先生の態度に敬意を表し、追悼を捧げます。
コーヒーが好きでした。その人生は、コーヒーのように薫り高く、周囲の人を癒してくれました。
フェルメールが好きでした。その人生は、強い意志を優しい光で包んだフェルメールの絵のように魅力的でした。
命あるものいずれは死と向かい合わなければなりませんが、最期まで人を気遣いながら旅立たれた岡島先生の態度に敬意を表し、追悼を捧げます。
No113.平成24年8月号 「お泊り保育」
夏といえば、子ども達が一番楽しみにしているのは、お泊り保育。今年は、ぜひ参加したい!と名乗りを上げた卒園児6名も含めて32名が大集合。そして、スペシャルゲストが来るよ!と聞かされていた子ども達は、育児休暇中の武内友里先生と3ケ月の赤ちゃんの突然の登場に驚きつつも、大喜びでした。恒例の花火大会もさることながら、今年のメインは、「ヒミツの迷路」と題して子ども達に内緒にしていた迷路仕立てのお化け屋敷。段ボールを繋げた全長10mのお化け迷路は、ハイハイで進入し、段々狭くなり途中からほふく前進。真っ暗闇の中を二人組で入って行きますが、泣く子が続出。どうしても入れない子を先導して私も入ってみたものの、行き止まりや仕掛けに阻まれ、四苦八苦。一度トンネルを抜けたところで鍵を受け取り、出口でお菓子に交換という仕組み。
以前、似た経験をしたことがあったなぁと思ったら、なんと旅先で訪れた長野県善光寺の「お戒壇めぐり」でした。真っ暗な回廊を抜け、錠前を探り当てると、ご褒美はお菓子ではなく、極楽浄土への道でしたが…
以前、似た経験をしたことがあったなぁと思ったら、なんと旅先で訪れた長野県善光寺の「お戒壇めぐり」でした。真っ暗な回廊を抜け、錠前を探り当てると、ご褒美はお菓子ではなく、極楽浄土への道でしたが…
No112.平成24年7月号 「七夕祭り」
日本中が猫も杓子も空を見上げた金環日食は、天体ブームが巻き起こし、流行に敏感な若い女性達の間では宙ガールが急増しているとか。昨今あまり人気のなかった日本古来の七夕の行事も、金環日食の余波で、今年は天の川を見上げ七夕を楽しむ人も増えるのではないでしょうか。保育現場では、流行り廃れなく年中行事として、毎年、子ども達は七夕祭りを楽しんでいます。今年も各クラスのお部屋には、願い事が書かれた短冊が飾られ、7月7日を迎える準備が着々と進んでいます。5日には、七夕発表会と称して、クラスごとに、みんなの前で発表をします。ヒヨコ組はダンスとリズム遊び、バンビ組はダンスと歌、パンダ組は「桃太郎」の劇を発表します。園庭で行う予定なので、晴れてくれるといいのですが…
七夕祭りといえば、仙台の七夕祭りが有名ですが、今年は、全国からの復興支援に対する感謝の気持ちを込めて、「願い、希望、感謝」をテーマにして開催するそうです。全国から願い事を募集しているので、私も送ってみました。インターネットで簡単に送れるので、皆様もお試しあれ!
七夕祭りといえば、仙台の七夕祭りが有名ですが、今年は、全国からの復興支援に対する感謝の気持ちを込めて、「願い、希望、感謝」をテーマにして開催するそうです。全国から願い事を募集しているので、私も送ってみました。インターネットで簡単に送れるので、皆様もお試しあれ!
No111.平成24年6月号 「天国へ逝ったアリス」
うさぎのアリスが保育園にやってきてから、かれこれ5年が経ちますが、先日、5月22日に急死してしまいました。前日、いつものように大きなうさぎ小屋で子ども達にたんぽぽのえさをもらってムシャムシャ食べて元気にしていましたが、その夜、ジーッと動かず、元気がありませんでした。翌日、病院に診せようと思っていましたが、朝を待たず亡くなってしまいました。
アリスは、今まで多くの子ども達を慰めてくれました。入園したばかりの子も、ママと別れられずに泣く子も、アリスを見せてあげたり、エサを一緒にあげたりすると、泣き止み、笑顔になって機嫌が直ります。アリスの魔法です。小動物達は、人間の大人にはできない、子どもを癒す、不思議な力があると感じます。言葉をうまく使えない子ども達は、小動物達とより近い存在なのでしょう。ダンゴ虫やハエや蚊でさえも、子ども達を元気にしてくれます。
今は、アリスの代わりに、金魚が水槽の中から子ども達を見守ってくれています。この金魚も、アリスと同様、近所の斉藤さんが持ってきてくれたものです。
生きとし生けるもの、終わる時はあることを子ども達もいつか知らねばならない時が来ます。アリスは天国へ逝った後も、子ども達に大切なことを教えてくれることでしょう。
アリスは、今まで多くの子ども達を慰めてくれました。入園したばかりの子も、ママと別れられずに泣く子も、アリスを見せてあげたり、エサを一緒にあげたりすると、泣き止み、笑顔になって機嫌が直ります。アリスの魔法です。小動物達は、人間の大人にはできない、子どもを癒す、不思議な力があると感じます。言葉をうまく使えない子ども達は、小動物達とより近い存在なのでしょう。ダンゴ虫やハエや蚊でさえも、子ども達を元気にしてくれます。
今は、アリスの代わりに、金魚が水槽の中から子ども達を見守ってくれています。この金魚も、アリスと同様、近所の斉藤さんが持ってきてくれたものです。
生きとし生けるもの、終わる時はあることを子ども達もいつか知らねばならない時が来ます。アリスは天国へ逝った後も、子ども達に大切なことを教えてくれることでしょう。
No110.平成24年5月号 「赤いカーネーションと黄色いバラ」
5月の第2日曜は母の日。保育園ではどのクラスもプレゼント作りに勤しんでいるところです。母の日の花といえば、赤いカーネーションですが、十字架に架けられたキリストを見送った聖母マリアが落とした涙から生じた花だと言われており、“母と子”や“母性愛“を象徴しているとのこと。
それでは、父の日の花といえば、何の花かご存知ですか。本来は白いバラの花でしたが、日本では黄色いバラが定着しました。幸せを呼ぶ色として、家庭のイベントには、ふさわしい色です。ママ、パパ、どうぞお子様からの手作りプレゼントをお楽しみにお待ちください。
それでは、父の日の花といえば、何の花かご存知ですか。本来は白いバラの花でしたが、日本では黄色いバラが定着しました。幸せを呼ぶ色として、家庭のイベントには、ふさわしい色です。ママ、パパ、どうぞお子様からの手作りプレゼントをお楽しみにお待ちください。
No109.平成24年4月号 「百名山踏破を目指せ」
卒園式を真近に控えた3月11日、きしくも東日本大震災と同じ日に、卒園児10名と保護者、職員を含め総勢34名で筑波山山頂を目指す登山に挑みました。
日本百名山の中で標高が一番低い877米の1000米に満たない山ですが、「西の富士、東の筑波」と称される名峰で、今話題のスカイツリーからも、その双耳峰の美しい姿が見られるということです。前日降った雪で、滅多に見られない雪化粧の筑波はとても美しかったのですが、滑りやすいので足場が悪く大変でした。しかし、誰も脱落者なく、全員が登頂に成功しました。大満足感を抱き下山する時の気分は爽快です。目指す山頂に向かって、一歩一歩登る過程は楽ではありませんが、苦しければ苦しい程、喜びは大きいものです。
登山のごとく、「目標に向かって努力する」という試練は、卒園後の子ども達の行く先には数知れず待ち受けています。卒園の門出に体験した筑波山登頂を事始めとして、百名山ならぬ百の目標に向かって臆することなく挑戦して百の頂上を極めてくれることを祈っています。
日本百名山の中で標高が一番低い877米の1000米に満たない山ですが、「西の富士、東の筑波」と称される名峰で、今話題のスカイツリーからも、その双耳峰の美しい姿が見られるということです。前日降った雪で、滅多に見られない雪化粧の筑波はとても美しかったのですが、滑りやすいので足場が悪く大変でした。しかし、誰も脱落者なく、全員が登頂に成功しました。大満足感を抱き下山する時の気分は爽快です。目指す山頂に向かって、一歩一歩登る過程は楽ではありませんが、苦しければ苦しい程、喜びは大きいものです。
登山のごとく、「目標に向かって努力する」という試練は、卒園後の子ども達の行く先には数知れず待ち受けています。卒園の門出に体験した筑波山登頂を事始めとして、百名山ならぬ百の目標に向かって臆することなく挑戦して百の頂上を極めてくれることを祈っています。
222件中 141-160件目