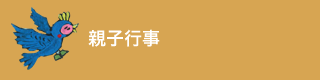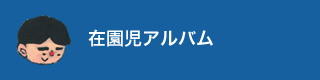水戸市笠原町の保育園・彩の国保育園。一時保育もお預けできます。
- トップ
- 保育雑感
保育雑感
No.186平成30年9月号 「平成最後の夏」
今年の夏も色々な事がありました。西日本集中豪雨、スポーツ界の不祥事、感動的な高校野球決勝戦の結末、アジアスポーツ大会での日本新記録達成などなど。オリンピックを二年後に控えて、スポーツ界が熱気を帯びているようです。
毎年色々な事が起こる夏ですが、日本人にとって忘れてはならないのが、8月15日終戦記念日です。今年は戦後73年目です。忘れ去られようとしている戦争の記憶ですが、戦争体験者の高齢化の中で、地道な活動により、毎年新たな記録や事実が発掘されています。その一つに「届かなかった手紙」を親族の元に届けようと活動を続けている人たちがいます。アメリカが戦利品として没収した日本兵が家族に宛てた何万通ともいわれる手紙が今少しずつ遺族の元に届けられています。遺骨も遺品も帰らなかった遺族にとって、本人直筆の手紙を75年後に受け取ることは、新たな悲しみに苦悩する事ではありますが、やっと戦争が終わった瞬間でもあります。戦争を知らない私達ですが、戦争体験者の人々の実話は、涙を禁じ得ません。一方、平成30年の戦没者慰霊式典は、「平成」最後の式典となりました。戦地巡礼の旅を長年にわたって続けてこられた天皇・皇后両陛下の慰霊の旅も終わろうとしていますが、戦後の様々な人々の「戦争を二度としてはならない」という信念に基づいた努力が73年間の平和を維持してきたとすれば、「平成」が終わろうともその努力を継承して、平和を守っていく責任をみんなで果たさなければならないでしょう。
No.185平成30年8月号 「猛暑を肝試しで乗り切ろう!」
No.184平成30年7月号 「オープン保育の真骨頂」
そこで、今月のオープン保育の様子をお話したいと思います。
まず、パンダ組の様子ですが、お部屋には大きないけすと小さないけすの2つが用意され、その中に魚がいっぱい泳いでいます。長い釣竿を持ったお兄さんお姉さん達は、大きいいけすで、短い釣竿を持ったちびちゃん達は、小さいいけすで魚を釣っています。釣った魚を回転寿司屋に持って行き、好きなお寿司を注文して席に座って待っていると、レーンにお寿司が出されるという仕組み。お店は大繁盛!大きい子に混じって、ヒヨコさん二人並んでお寿司を食べている姿は微笑ましく、思わず、パチリ!バンビ組には、昭和レトロな駄菓子屋さんが出現。大人も、子供時代にタイムスリップしそうな、わたがし、せんべい、ドーナツ、プリン、ラムネ等々沢山の駄菓子が箱に入ってお行儀よく並んでいます。お兄さんお姉さん店員が、ちびちゃん達に優しくお菓子を売っています。部屋の角には、ボウリングコーナーが設置され、子供達で大賑わい。わたあめ大好きな女の子がイート・イン・コーナーでわたがしを食べている姿を2回も見かけました。ヒヨコ組には大きなトンネルが設置され線路の上を色々な電車が走り回っています。紐電車、牛乳パック電車、大きい子が小さい子を乗せてひっぱる段ボール電車、マジックテープで連結するフェルト電車。先生のアイデアが光ります。
終わった後、子供から嬉しい一言を貰いました。ボウリングでただ一人ストライクを出した年長さんに「すごかったね!!」と声を掛けると、「今度のオープン保育は幾つ寝るとやるの?」
そうきたか!次回は、もっと先生達はりきっちゃうぞ!!
No.183平成30年6月号 「子供とお年寄りの触れ合い ―0歳から90歳までー」
このようなお年寄りの存在は、子供達にとっても無くてはならないものです。
身近にいるお年寄りに日本文化を教えてもらったり、一緒に歌を歌ったりする中で、可愛がってもらい慈愛の心に触れることは、子供の心の成長を育みます。
また、長い人生の中で習得した知恵を授けることができるのもお年寄りです。彩の国保育園の子ども達と接する度に、口を揃えて「子は宝」と皆さんはおっしゃいます。子という原石を磨いて宝石にする役割の一旦を荷うことができるお年寄りも、また宝ではないでしょうか。子供、お年寄りばかりではなく、青年も、中年も人はみな宝。人の尊厳を大切にし、人命を尊重する社会は、世代の隔絶からは産まれないでしょう。
楊箸さんの礼状の中にこんな一文がありました。
「この度は、否、この度も掛け替えのない楽しい時を過ごさせていただきました。園児達の可愛い眼差しや琴線に触れる好奇心の様子には瞠る(みひらかれる)思いでした。一緒に童謡を歌ってすっかり若返りました。つい齢も忘れて・・・はち切れそうな園児達の声が耳に残ります。」
子供もお年寄りの力になっているのですね。世代間で相互に与え与えられる関係を築いて行けば、人間性豊かな社会が生まれ、喜びや幸せをいっぱい感じる人生を歩むことができるのではないでしょうか。
No.182平成30年5月号 「子供は折り紙が大好き」
私達大人も、子供の頃に折り紙で遊んだことがないと言う人は、たぶん一人もいないことでしょう。奴さんやヒコーキ、チューリップなどはポピュラーですが、その中でも、鶴は、世代を問わず、日本人なら誰も一度は折った事があるに違いありません。折り鶴は、日本だけでなく、今や世界平和の象徴として海外でも注目されています。
さて、折り紙の起源ですが、七世紀に神事や儀式に用いられた事に始まりますが、江戸時代になり庶民の遊びとして広まり、明治以降、幼児教育に取り入れられ、子供文化として親しまれるようになりました。現在では、「origami」として、世界中の人に愛され、芸術作品を生み出すほどの進化を遂げています。
このように、世代を問わず世界中の老若男女を魅了する折り紙ですが、子供達にとっては、折り紙の何が面白いのでしょうか?夢中になっている子供達を観察してみると、いくつかその理由が見えてきます。
キーワードは、
①たくさん ②カラフル ③変化 ④何度でも ⑤増えるでしょうか。沢山ある中から選べる楽しさ、好みの色を選べる喜び、折るたびに形を変える面白さ、「もう1回!」という欲求が何度でも満たされ、そして、最後は出来上がった自作作品を沢山集めて充実感に浸ることが出来ます。現在人気のDYIの幼児版とも言えるでしょうか。
一方、与える方にとっては、指先を使い、創造力を促す折り紙は、教育的意義も高いと言えます。また、大人にとっても、老化防止に役立つこと受け合いです。「いつでも、どこでも、だれでも」楽しめる折り紙は、これからも世界中にどんどん広がりその可能性をどんどん発揮して世界文化と呼べるようになることでしょう。
No.181平成30年4月号 「煮干し」
2日後の卒園式では、8名の卒園児とA君が重なり、一人一人の高校生姿を思い浮かべながら、「伸びろ、伸びろ、天まで伸びて、大きくなれ!」と祈り、送りだしました。
いつの頃からか、おやつに煮干しを出さなくなりなしたが、「煮干し」の力を信じて、またおやつに出そうと思います。その効果を実証してくれる卒園生が、訪ねてくれる日を期待して・・・。
No.180平成30年3月号 「親と保育士の願いは、子の健康と成長」
従来、園での節分行事は、子供たちだけで、豆まきをしていましたが、今年は初めて親子参加行事として開催することになりました。立春を祝い、子供の無病息災を願う節分にちなんで、保護者の皆様と共に、昨年一年間の子供達の成長を確かめ、この先一年の健康と成長を願うことを主旨として開催致しました。第1部の各クラス発表は、一年間継続して取り組んできた活動のひとつを見て頂きました。パンダ組はピアニカと音楽リズム、バンビ組は劇遊び、ヒヨコ組は手作り楽器を用いたリズム遊びと絵本による言葉遊びを発表に取り上げました。初めての取り組みで、試行錯誤を重ねながら一歩ずつ前に進んできましたが、継続することで得られたものは、子供達の血となり肉となっていると感じています。パンダ組の子供達は、根気や意欲、そして向上心を、バンビ組の子供達は劇遊びを通して社会の入口を知り、つもり行動を重ねて世界観を広げてきました。ヒヨコ組の子供達は、手作り楽器で色々な音に触れ、聞き分ける力を養い、絵本でことばの面白さを知りました。次の一年を生きる栄養や力を蓄えてくれたと信じています。第2部では、「鬼は外、福は内」を戸外で盛大に行う計画を立てていましたが、天候に阻まれてしまい、とても残念でした。しかし、室内では、親、子、先生が、一同に会し、今までにない一体感を感じながら、特技を見て、驚き、笑い、仮装のキャラクターに感心、感動、お菓子をもらう子供達の喜びの笑顔、大人も童心に帰り、子供達と一緒に楽しい一時を過ごすことができました。会場の狭さや進行等、色々不備なこともあり、改善点は多々ありましたが、保護者の皆様の温かいご支援により、素敵な会になった事、心より感謝申し上げます。保護者の皆様のお力をお借りすることで、子供達の笑顔や喜ぶ姿をいっぱい見る事が出来ました。本当にありがとうございました。私たち保育士にとっても、次年度に繋がる貴重な体験となりました。来年度は、私たち自身も向上心を持ち、更に、保育の質を高めるよう努めて参りたいと思います。
No.179平成30年2月号 「日本文化と鬼」
節分の豆まきは、日本古来の行事として、地域や家庭の中で受け継がれており、老若男女が楽しめる大衆文化と言ってもよいのではないでしょうか。
元来、日本文化と鬼は、深い関係があり、現代の私達の生活の中にも、鬼はしっかりと根付いています。それもそのはず、昔話や地域の祭事には、怖い鬼、優しい鬼、ユーモラスな鬼など様々な鬼が登場し、小さいうちから子供達は鬼に恐れを抱いたり、泣かされたり、笑わされたりして、育ってきている訳ですから。一年間の無病息災を願い、鬼を追い払う節分の豆まきは、日本各地の神社やお寺で節分会又は節分祭として、毎年盛大に行われています。人気力士が招かれる成田山新勝寺や、力道山のお墓がある由縁で、プロレスラーが招かれる池上本門寺がよく知られています。
保育園でも、今年は、「ア○○○○ン」を始め、子供達が大喜びしそうなお客様を多勢呼んで、保護者の皆様と一緒に節分祭を楽しむ企画をしています。
また、各クラスがこの一年間継続的に取り組んできた活動の発表会も行います。今までの一年間の成長を喜び、これからの一年間の成長を祈願する行事として、年間行事の中に、取り入れていく予定です。平日の開催となり、お忙しいこととは思いますが、子供達と一緒に楽しい催しに致しましょう。
No.178平成30年1月号 「絵本で一年を振り返り、絵本で新年を迎える」
彩の国保育園の一年も、色々なことがありましたが、中でも、素晴らしい出来事は、彩の国図書館で本を借りてくれる人が増えたことです。
ボランティアの方々による絵本の読み聞かせを長年続けてきましたが、年を重ねるごとに子供達は絵本に集中するようになってきました。
一方、各クラスで、毎日、月刊絵本を読む時間を設けていることも、絵本を読む習慣に繋がっているかと思われます。また、図書係の先生達が、もっと絵本を好きになってもらい、図書館に足を運んでもらおうと、色々な工夫をしていることも、一役かっていると思われます。
更に、お忙しいにも関わらず、お子様が「本を借りたい」と言うと、一緒に図書館へ入り、本を選んだり、感想を書いたり、保護者の皆様のご協力も、絵本の貸し出し冊数の増加に繋がっていることと思います。
幼児期は、お父さん、お母さんと一緒に絵本を読むことが大切だと言われています。絵本は言葉や知識を学ぶためだけのものではなく、親と子の愛情を育むことも出来ます。夜、布団に入って読んでもらった絵本は、母親の温かさと共に、ず-っと心に残るものです。
ところで、お子様と読んだ絵本の中で、今年一番のお気に入りの絵本は何でしたでしょうか?ちなみに、貸し出しNo1.絵本は「おしり探偵」でした!
参考までに、世間の絵本売上年間ランキング一位は、「えんとつ町のプぺル」、年間ベストセラーNo1.は「90歳、何がめでたい」でした。
興味がある方は、お正月に是非読んでみて下さい。「一年の計は元旦にあり」平成30年の読書計画も立ててみてはいかがでしょうか。
No.177平成29年12月号 「Xマスの光と陰」
ところで、Xマスといえば、思い浮かぶ絵本にアンデルセンの「マッチ売りの少女」があります。皆様もご存知でしょうが悲しいお話です。楽しいXマスだからこそ強く印象に残っていますが、貧困と死を描いた絵本を、好んで子どもに読んであげようと思う親は、今の時代にはあまりいないでしょう。子供達が大人になった時、Xマスに「マッチ売りの少女」を思い出すことはないかも知れません。アンデルセンが書いた童話には、他にも「みにくいアヒルの子」「人魚姫」「裸の王様」「絵のない絵本」など名作ぞろいです。彼は、自分の様々な人生経験で得た教訓を、童話という形にして、子供達にも分かりやすく伝える作品を残しました。作品の文中から、その物語の教訓と思われる文章を拾ってみます。
「みにくいアヒルの子」には、「自分がみにくいアヒルだと思っていた頃は、こんな沢山の幸せがあるなんて、思ってもみなかった。」と言う一文があります。
「人魚姫」には、「人間は、ほとんど常に感情の色めがねを通して世界を見るもので、そのレンズの色次第で、外界は暗黒にも深紅色にも見えるのです。」とあります。
教訓が分かりやすい作品は、未だに人気があるようです。「マッチ売りの少女」を描いた作者の意図を知るために、もう一度深く作品を掘り下げて読んでみたいと思います。「貧困」や「死」というテーマは人間の永遠のテーマと言えますし、子供の頃に読んでもらった絵本はずっと心に残り、大人になって生きる力になることもあるのですから。
最後にアンデルセンの名言を1つご紹介します。
「すべての人間の一生は、神の手によって書かれた童話にすぎない。」
No.176平成29年11月号 「雨の日の運動会」
天気出現率という気象データーは10/9~10/31までは晴れマークがずっと続いています。1964年の東京オリンピックの開会式の日にちを決める時にも、晴れる確率が高い10/15か10/10が候補に挙がり、土曜日だった10日に決定されたいきさつがありました。以後、体育の日として2000年まで祝日となり、晴れる特異日として広く認識されるようになりましたが、正確に言うと10月10日は、特異日ではなく、11月3日(文化の日)が正真正銘の晴れの特異日とのことです。話が脱線してしまいましたが、そんな訳で10月13日の運動会は、晴天の秋空の下で、行われるはずだったのです。
ところが、近年の異常気象のせいか気象データーに異変が生じ、13日の前後は連日雨予報。できないかもしれないという不安は当日の朝まで続きましたが、何とか大量の水たまりを汲み出し、開催にこぎつけたものの、入場行進が始まると同時に、またしても、無情の雨が子供達の頭上に落ちてきました。
途中打ち切らざるを得ないと弱気になっていましたが、そんな大人達を尻目に、子供達のパワーはいつもと変わらないというよりは、それ以上でした。雨をものともせず、演技に集中する子供達の姿に励まされながら、とうとうすべての演目を予定通りこなし、雨の日の運動会は無事終了しました。
私達大人は、子供を導く存在ですが、逆に、子供に教えられることは、多々あります。今回も、子供達の運動会をやりたいという一途な思いと、運動会を楽しむ天真爛漫な笑顔が、私達を導いてくれました。親として、保育士として「子供に学ぶ」謙虚な姿勢を忘れない様にしたいものです。
蛇足ですが、2020年東京オリンピックの開会式は7月24日(金)です。その年の10月12日(月)の体育の日をスライドして、この年だけ開会式の日を祝日にする案が出ているそうですが、いかがなものでしょうか?
No.175平成29年10月号 「ちびっこアスリート、記録に挑戦」
9月9日は、今ではほとんど忘れさられていますが、「重陽の節句」です。
「菊の節句」とも言われ不老長寿や繁栄を願う行事として、昔からお祝いされてきた五節句の一つです。9(陽数)が重なるので、重陽と言われますが、今年の9月9日はもう一つ9が重なり、日本中が大喜びしました。それは、日本陸上界待望の男子100m9秒台が、桐生選手によって、打ち立てられた日となったからです。世界初の9秒台から遅れること約半世紀、日本記録の更新は19年ぶりですから、長かった「10秒の壁」をやっと破った、一大快挙です。
スポーツの世界は、常に記録との戦いであり、記録の限界を目指して、後から後から記録が塗り替えられていきますが、今、彩の国保育園でも、ちびっこアスリート達によって、日々、記録の更新がなされています。運動会を間近に控え、子供達の間でなわとび熱が高まっていて、なわとびを跳ぶ回数の記録が、日々更新されています。10回跳んだ子は、「今度は、20回跳ぶ」、100回跳んだ子は、「次は、200回跳びたい」と、自己目標を掲げて、なわとびに夢中になっています。中には「無限に跳びたい」と言い出す子まで・・・今日も、昨日435回跳んだばかりの子が、515回跳んで、一日で記録を更新しました。子供の気力や体力は、大人顔負けです。
現在、最高記録は、696回ですが、700回、800回、900回、そして、1000回の大台にのる日もそう遠くはないでしょう。ちなみに、男子100mの限界予知値は9秒48と言われていますが、果たして、子供達の縄跳び回数限界予知値は?子供達に聞けば、無限と言うに違いありません。
No.174平成29年9月号 「ダンゴ虫さんどこへ行ったの?」
今年の夏、彩の国保育園に遊びに来た虫は、とても少なく、私が見かけた限りの種類と数を数えてみると、“カナブン3匹、アゲハ3匹、モンシロチョウ6匹、てんとうむし6匹、バッタ1匹、カミキリムシ2匹、トンボ15匹”です。桃の木の下にクローバー畑を作ったかいもなく、例年に比べて、昆虫が少ない淋しい夏です。かれこれ2,30年前から徐々に減ってきた昆虫ですが、ダンゴ虫だけはいつでもいっぱいいたのに、今年はとうとうダンゴ虫まで少なくなってしまいました。先日、子供達がダンゴ虫の家を作ったので、ダンゴ虫を探すことになりました。
駐車場のフェンス添い、ヒヨコ組の脇のスペース、玄関脇の庭の石下など、くまなく探しましたが、見つかったのはたった一匹。一体どこに行ってしまったのでしょう。いなくなってみると、ダンゴ虫が更に愛おしく感じられます。昆虫の減少を食い止めようと、海外では、インセクトホテルが作られていると以前紹介しましたが、東京にも、「生物多様性」をテーマにした庭が、森ビルにあるようです。また、今年話題になったGINZASIXの空中庭園には多種類の植物が植えられていて、銀座の空に虫がいっぱい飛び交う日がくるかもしれません。最近では、個人の庭に作るバグホテルも注目されています。クローバー畑の中に、廃材のボードで、枠を作り、その隙間に、薪、わら、コルク、小枝や松ぼっくりを詰めて、バグホテルを作ったら、ダンゴ虫さんも泊まりに来てくれるでしょうか・・・・?
No.173平成29年8月号 「継続は遊びなり」
七夕発表会が7月7日、20名ほどの保護者の参加のもと、賑やかに行われました。
本年度は初めて、全クラスが発表を行いました。ヒヨコ組はしまじろうの曲でダンスを披露し、バンビ組は歌とダンス、パンダ組はキラキラ星の合奏を発表しました。新しいクラスになって、先生やお友達とも馴染み、ようやくクラスとしてのまとまりが出てくるこの時期の発表だったにしては、子供達は良く頑張ったと思います。
保護者の方々からも、子供の成長が見られたという声が聞かれました。
お父さんやお母さんの顔を見ると、ヒヨコやバンビの中には大泣きして、普段通りに踊ったり、歌ったりできなくなってしまった子もいましたが、それも、成長には欠かせない良い経験だったと思います。
本年度は、「日々の積み重ね」を目標に掲げて、活動の継続を重視していますが、ピアニカもそのひとつです。ピアニカを縦にして弾く奏法を新しく取り入れたので、なかなか定着するまでには時間がかかりましたが、見事にマスターしました。また、年中さんが、初めてピアニカ演奏に挑戦し、年長さんとの共演を果たしたのも、継続の力に因るところが大きいと思われます。
しかし、継続といっても、色々なことを遊びから学んでいくのが子供ですから、その本性をないがしろにしては本末転倒になりかねません。子供の興味関心を引き出し、意欲を高めるには、一工夫も二工夫も必要です。大人が『継続は力なり』なら、子供は『継続は遊びなり』と言えるでしょうか。どのクラスも今年は、長期的な見通しを立てて、活動に臨んでいますが、これから、子供達はどのような継続的遊びを展開していくのでしょうか?七夕発表を見て、期待が高まりました。
No.172平成29年7月号 「人間も虫や花と同じ生き物」
「ファーブル昆虫記」と言えば、知らない人はいないと思いますが、「日本のファーブル」と呼ばれる熊田千佳慕(くまだちかぼ)の絵本を読んだことがある方は、あまりいらっしゃらないのではないでしょうか。彼の描く虫たちは「クマダの絵は生きている」と世界でも高い評価を受けています。どんな腕のいい写真家が撮映した虫よりも本物らしく、というより、今にも絵本から飛び出してきそうな本物そのものといった感じです。彼の自然観察は人並みはずれた観察法で、3時間でも4時間でも納得がいくまで、虫や草花を眺めて、草原に這いつくばっているので、行き倒れの老人と間違えられることも、しばしばあったということです。特に絵本作家になってからは、小さい子供達に見せる絵に嘘があってはいけないと、「見て、見つめて、見極める」ことを心掛け、その結果「私は虫であり、虫は私である」「私は花であり、花は私である」という境地にまで行きつきました。
99歳で亡くなるまで、毎日虫や花と遊び、小さな命の美しさを筆一本で表現し続けました。命や自然の大切さを子供達に伝えたい、お母さんたちに知ってもらいたいという一心から、描き続けたそうです。自然を知らずに大人になる時代に警鐘を鳴らし続けたとも言えます。
「自然は美しいから美しいのではなく愛するから美しいのです。」という彼の言葉からは、人間らしく生きるために、自然を大切にしなさいというメッセージが伝わってきます。
7月の新刊として図書室に備えますので、是非借りていただきたいと思います。お家でお子様と一緒に、虫の可愛さ、草花の美しさをご堪能いただき、自然を大切にする気持ちを育んでいただければと思います。
No.171平成29年6月号 「歴史が築き上げた日本文化の魅力 ~初夏に舞う艶やかな着物姿と雅な琴の音~」
彩の国保育園の北側には、住宅街が広がっており、その住民の中には、保育園を支えて下さっている方々が何人もいらっしゃいます。
本日「お琴と日本舞踊を観る会」で演技を披露して下さったのもこの地域にお住いの方々です。この一画は、低層住居地域に指定されている為、一階住宅が多く、良好な住環境で、県庁が建つ前からある、昭和の匂がする古き良き住宅街です。住人は、子育てを終えた高齢の方が多く、人生経験豊かで、教養、知識にも富み、社会的活動にも熱心な方々です。
“子供は社会の宝”と言って、地域が子育てを荷った世代の方々なので、保育園に対する理解もあり、協力的で、子供達に色々な体験を提供して下さいます。
今日の催しは、今の子供達にはほとんど馴染みのない、日本古来のお琴と日本舞踊という事で、子供達は興味津々でした。聞き慣れない琴の調べ、見慣れない艶やかな着物姿の優雅な舞いに、子供達も見とれていました。“さくらさくら”の曲が流れると「♪さくら~さくら~」と一緒に口ずさむ子、クルクル回る傘をじっと見つめる子、日本的文化を知る貴重な体験となりました。舞踊の後は、お琴の伴奏で子供達が歌う番。初めてお琴に合わせて歌いました。
子供達の元気な歌声にお琴の先生は、お顔がパァ-ッと明るくなりました。“こいのぼり”“めだかのがっこう”等、代々受け継がれてきた日本の歌が、世代を越えて、両者を繋いでくれたひと時でした。
最後に、本物のお琴に手で触れさせて下さいました。今日の体験が、子供達の心と体の中に記憶されていづれ日本文化の理解に役立ってくれることを願います。




No.170平成29年5月号 「園庭の穴」
園庭のあちこちに大きい穴や小さい穴が点在していて、雨が降った後は、水たまりができるので、その穴の所在がはっきりわかるのですが、最近穴が増えてきています。この大小の穴たちは、子供達のしわざです。このままいくと、園庭が穴ぼこだらけになりかねないので、穴を掘っている所を目撃すると、現場に急行して、現行犯注意をしてパトロールを強化しています。しかし、一向に子供達の穴掘りに歯止めはかかりません。というのも、子供達は穴掘りが大大大好きなんです。その理由は、穴を掘る行為そのものが面白い上に、虫を探す、黒い土を集めるという目的が重なると、どんどん穴が掘り進められて建物や総合遊具の土台が露出している深い穴も2ケ所あるほどです。「雨だれ石を穿(うが)つ」と言いますが、「子供の穴掘り家が傾く」と言っても大げさではありません。そこで、従来は砂場であるところに、砂ではなく黒土を入れて「土場」を作ってみました。子供達が、土に求めているものは、その感触と可塑性です。土を触ると「冷たくて気持ちがいい」「きめ細かくつるつるで気持ちがいい」等の心地よい刺激があります。手で丸めれば、お団子になったり、型にはめれば、プリンになったり、色々な形を作ることが出来ます。砂にはない土の特性が子供の遊びの幅を広げてくれます。2、3日前踏み固められた「土場」の土をくずして土のブロックをチョコレートに見立てて、入れ物にいっぱい集めて遊ぶ姿が見られました。これから「土場」でどんな遊びが展開されるのか見守っていきたいと思います。それに、「土場」は園庭の穴掘りに歯止めをかけてくれる存在になり得るのかも興味のある所です。果たして子供達は「土場」の中だけで穴を掘って満足してくれるものでしょうか・・・・・?
No.169平成29年4月号 「新たな保育の試みに向けて」
一つは、「年長お手伝いの日」を設け、バンビ組やヒヨコ組に年長さんがお手伝いに行きます。手始めに、4/19(水)に、新年長さんは、バンビ組に出かけて、バンビ組の先生の指導のもとで、バンビ組の子供達と一緒に遊びます。果たして、年長お手伝い隊には、どんな任務が課せられるのでしょうか?隊員の活躍を期待します。
もう一つの取り組みは「オープン保育」と称して、全園児が一斉に、自分の好きな遊びを選んで、クラスの壁を取り払い、混じり合って遊ぶという試みです。初回は4/26 (水)に予定しています。その日は、ヒヨコの部屋はおままごと、バンビの部屋はおえかき、パンダの部屋は新聞紙遊びを用意します。好きな所に行って誰と一緒に遊んでもかまいません。果たして、どんな関わりが生まれ、どんな遊びが見られるでしょうか。このふたつの取り組みは、様子を見ながら、回数を増やして行きたいと思っています。また、内容も工夫して、自主的、創造的な遊びが展開できるような活動にして行きたいと思います。
この他に、今年度は、各クラスで、一年間を通して、継続的に行う活動を決めて、日常的に子供の発育を見守る保育に取り組む一方、自然との関わりから学ぶ保育にも力を入れたいと思っています。昨年は、昆虫ブームが子供達の遊びの幅を広げました。図鑑を引っ張り出して、虫の名前やエサを調べたり、皆で頭を寄せ合って観察したり、虫が一匹いれば、他のオモチャはいりませんでした。自然が少ない環境のなか、お散歩を増やすなど、工夫をしてなんとか、自然を保育に取り込んで行きたいと思っています。
新しい取り組みや自然との関わりなど、アイデアや工夫を生み出す柔らかい発想が必要なので、保護者の皆様のご協力もお願いしながら、進めていきたいと思っています。
No.168平成29年3月号 「 絵本の力 」
さて、この一冊をはじめ、毎月の新刊や、卒園児等からの寄贈により冊数も徐々に増えてきた彩の国図書館ですが、貸し出しを始めてから、もうすぐ一年になります。徐々に貸し出し冊数も増えており、親子で絵本を楽しんでもらいたいという先生達の企画も軌道にのってきました。保護者の方々の感想も、子供達の借りたい気持ちを後押ししているものと思います。ネット社会の中で生きる子供達の子守役が、テレビやビデオやスマホにならないように、絵本にはもっともっと頑張ってもらいたいものです。パンダ組のT君のママは、「食事中にテレビは見ない、スマホを与えない。」という約束をして、子供との会話を増やすようにしたそうです。注意散漫による集中力の低下、感受性の低下、社会的スキルの低下等の悪影響により、子供の成長を蝕むといわれる情報機器に頼らない子育てに、絵本は、大いにその力を発揮することができます。「子どもはみんな問題児。」の中に、絵本の力を最大限に引き出す方法が書いてあります。一冊の絵本の持つ力は、その絵本を読むお母さん、お父さんの持ち味や、工夫や努力で何倍にもなります。絵本の魅力は、こんな所にもあるようです。
No.167平成29年2月号 「世界でいちばん貧しい大統領と世界でいちばんお金持ちな大統領」
ところで、世界中が注目する中、二十日の就任式で「世界でいちばんお金持ちな大統領」になったドナルド・トランプ大統領ですが、その総資産額は40億ドル(5000億円)とも言われ、自宅は、トランプタワー最上階の部屋数がなんと20以上もある大豪邸で、金ピカの調度品に囲まれて暮らしているそうです。そんな彼にとって、「世界でいちばん貧しい大統領」の数ある名言中の名言「お金持ちは政治家になってはいけない」と言われたら、何と答えるでしょうか。年俸40万ドル(4300万円)を受け取らないといっているトランプ氏の考えることは、一般庶民には及びもつきませんね。
222件中 81-100件目